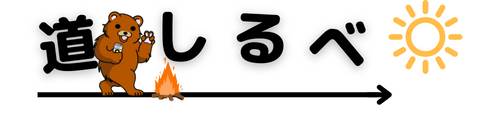いよいよ秋も終盤。
紅葉も落ち着いて、冬の足音が聞こえてきました。
八甲田山頂も10月15日に初冠雪。(2020年)

平年より2日早く、去年より21日早いらしいですよ。
豪雪地帯でもある青森県内のキャンプ場は殆どが10月末で冬季閉鎖となりますので、雪中キャンプをしない限りは今シーズンのキャンプは終わりですねぇ。
前置きが少し長くなりましたが、今回は焚き火に使う薪についてのお話しです。

焚き火に適した薪とは?
焚き火には乾燥した3種類の大きさの薪を用意する事をおすすめします。
大きさはともかく乾燥は薪を選ぶ第一条件です。
乾燥していること
なぜ乾燥していることが第一条件なのか?
生木や濡れた薪だと水分が邪魔して着火しづらい。
さらに着火しづらいうえに煙が大量に出て周囲にも不快な思いをさせる。

乾燥した薪だと着火しやすいうえに煙も殆ど発生しないですよ~。

針葉樹と広葉樹を使い分ける
一口に薪と言っても、針葉樹・広葉樹との2種類に分けられます。

針葉樹と広葉樹の特徴を理解し上手に使い分けると、もっと焚き火が楽しくなりますよ。
針葉樹の特徴
針葉樹の薪は油分を多く含んでいて燃えやすいので最初の火おこし時に細めの針葉樹を使うと火おこしが楽になります。
その分、火持ちが悪く、油分を含んでいるので煙・臭い・煤が多め。

松ぼっくりは着火剤代わりに重宝しますよ。
広葉樹の特徴
広葉樹の薪は密度が高いので重量があり火がつきにくいが、火持ちが良く油分も少ないので煙・臭い・煤は少なめ。
焚き火で火が育ってから投入するとよいです。
3種類の大きさを用意する
絶対条件ではありませんが大中小(太中細)の3種類を用意しておくと火おこしも楽ですし、調理時の火力調整もしやすいうえにのんびりと焚き火を満喫することができます。
針葉樹・広葉樹の使い分けと同様に、用途によって大きさの違う薪を使い分けることで、より一層焚き火が安全で楽しいものになります。
細い薪(火おこし・焚き付けに適してる)
最初に火をつける時に使う。
針葉樹のほうが燃えやすいので細めの針葉樹を使うと火おこしが楽になります。
現地でキャンプ場や森林を歩いて拾うこともできる。
中くらいの薪(火力調整に適してる)
火がついたら中くらいの薪を入れて火を大きくしていきしょう。
調理のさいの火力調整に細~中程度の広葉樹を使うと煤も少なく火持ちもそれなりに良いので、調理器具への煤がつきにくく調理もしやすくなります。
太い薪(長時間の燃焼に適してる)
焚き火でせかせかと薪をいれているとせっかくの火の揺らめきを楽しむはずが、ただただ火の管理で忙しい思いをしてしまいます。
のんびりと焚き火を楽しむなら太めの薪を入れて、あとはゆったりとグラスを傾けましょう♪

木の種類による特徴
針葉樹・広葉樹の中でも更に種類によって火持ち・火力・香りなど違いがありますので、一般的に良く使われる薪を何種類か紹介します。
針葉樹
- スギ
比較的手に入りやすく安価。
柔らかく薪割りしやすいが燃えが早く火持ちが悪い。- ヒノキ
針葉樹の中では比較的火持ちがよい。
ヒノキの香りが好きで好んで使う方もいます。- マツ
油分が多いので火つきがよいが、その分煙の量も多い。
松ぼっくりなどと一緒に火おこしように使うとよい。
広葉樹
- ナラ
手に入りやすく火持ち・火力ともによい。
薪ストーブにも最適で日本ではポピュラーでコスパに優れた薪。- ケヤキ
とても固く薪割りには少々苦労する。
ナラには劣るものの着火性・火持ちは良く、独特の香りも特徴の一つ。- カシ
「薪の王様」の異名をもつカシ。
火力・火持ちは最高峰で長い時間燃え続ける。- サクラ
甘い香りが特徴的でスモークチップにもよく使われる。
火力・火持ちはナラやカシに比べると劣る。